
もしも、大きな地震が起きて、家族と離れ離れになってしまったら…

電話が通じなくなったら、どうやって家族の安否を確認すればいいの?

あなたは、そんな切実な不安を抱えていませんか?
私の父が土砂崩れに巻き込まれかけた経験から、防災の重要性を痛感した私自身も、災害時の家族との連絡方法については特に不安を感じていました。しかし、公的機関が提供するサービスや、災害を経験した方々の知恵を学ぶことで、電話が使えない状況でも、大切な人と連絡を取り合う方法があることを知りました。
この記事を読めば、いざという時も慌てずに家族の安否を確認できる方法が分かり、漠然とした不安から解放されます。災害用伝言ダイヤルの使い方から、家族で事前に話し合っておくべきことまで、具体的に解説しますので、ぜひ最後まで読んで、あなたのご家族の安心を手に入れてください。
なぜ災害時は電話がつながりにくいのか?
災害が発生すると、多くの人が一斉に電話をかけるため、電話回線がパンクし、通話が非常に不安定になります。これを「輻輳(ふくそう)」と呼びます。
この輻輳を避けるため、携帯電話会社は通話の通信量を制限することがあります。そのため、電話をかけても「ただいま回線が大変混み合っております」というアナウンスが流れ、なかなか繋がりません。
しかし、音声通話の代わりに、インターネット回線(データ通信)は比較的繋がりやすい傾向にあります。そのため、電話以外の方法を事前に決めておくことが非常に重要になります。
災害時に知っておきたい安否確認の方法
ここでは、電話がつながらない状況でも役立つ、安否確認の方法をいくつかご紹介します。
1. 災害用伝言ダイヤル(171)
災害用伝言ダイヤル「171」は、NTTが提供する音声伝言サービスです。被災地から離れている家族や友人が、安否確認のために利用できます。
- 使い方:
- 「171」に電話をかけ、ガイダンスに従います。
- 伝言を録音したい場合は「1」、聞きたい場合は「2」を押します。
- 自宅の電話番号などを入力し、伝言を録音または再生します。
2. 災害用伝言板(web171)
災害用伝言板「web171」は、インターネット上で安否情報を確認・登録できるサービスです。文字でメッセージを残せるため、音声を聞き取ることが難しい場所でも利用できます。
3. SNSやアプリ
災害時は、TwitterやFacebookなどのSNSや、LINEのようなメッセージアプリが、安否確認のツールとして非常に有効です。
- Twitter: ハッシュタグ(例:「#安否確認」)を使って、安否情報を発信・検索できます。
- LINE: 災害用安否確認機能「安否確認」を使い、無事を簡単に家族や友人に伝えられます。
これらのツールは、電話回線とは異なる通信経路を使うため、比較的繋がりやすいとされています。ただし、サーバーがダウンする可能性もあるため、複数の手段を確保しておくことが大切です。
家族で話し合うべき「もしもの時のルール」
災害時にパニックにならず、冷静に行動するためには、事前の話し合いが不可欠です。ぜひ、ご家族で以下の3つのルールを決めておきましょう。
1. 集合場所の取り決め
自宅が被災してしまった場合、どこで家族と合流するかを事前に決めておきましょう。
- 第一集合場所: 自宅から徒歩圏内にある安全な場所(近所の公園、コンビニなど)。
- 第二集合場所: 自宅から少し離れた避難所など。
2. 連絡方法のルール
誰が誰に連絡するか、使う連絡ツールの優先順位を決めておきましょう。
- 第一優先: 災害用伝言ダイヤル(171)
- 第二優先: LINE、TwitterなどのSNS
- 第三優先: 公衆電話など
3. 各自の役割分担
家族それぞれの役割を決めておくと、いざという時にスムーズに行動できます。
- 例: 「お父さんは備蓄品の確認」「お母さんは貴重品の持ち出し」「子どもはペットの保護」など。
まとめ
災害時、家族と連絡が取れないことほど不安なことはありません。しかし、事前に安否確認の方法を学び、家族で話し合っておくことで、その不安は大きく軽減されます。
この記事でご紹介した内容を参考に、あなたの大切な家族を守るための「もしもの時のルール」を、今日から話し合ってみませんか?
今日から始める小さな一歩が、いざという時の大きな安心につながります。
防災リュックについて詳しく知りたい方はこちら
防災トイレについて詳しく知りたい方はこちら
防災水について詳しく知りたい方はこちら
防災食料品について詳しく知りたい方はこちら
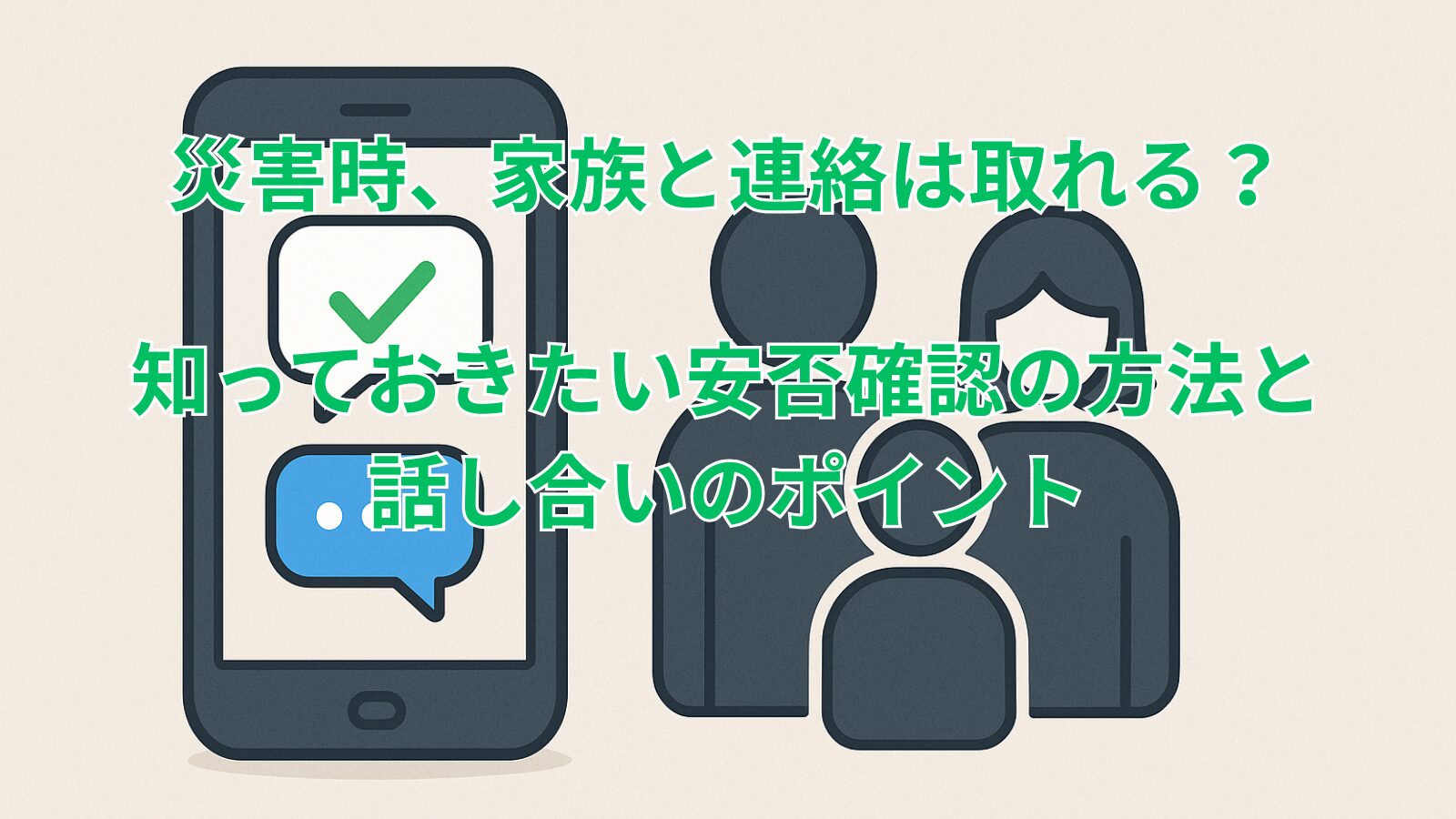

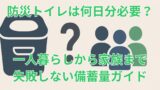
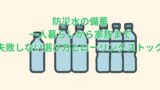



コメント