
非常用トイレって、どれくらい備蓄すればいいんだろう…?

場所を取るし、使わずに無駄になったらどうしよう…

あなたは、そんな不安を抱えていませんか?
私の父が土砂崩れに巻き込まれかけた経験から、防災の重要性を痛感した私自身も、防災トイレの備蓄については多くの悩みを抱えていました。しかし、公的機関が推奨する備蓄量や、災害経験者の声、そして専門家の知恵を学ぶことで、防災トイレがいざという時の安心感を大きく左右する、非常に重要な備えだと気づきました。
この記事を読めば、あなたの家族構成に合った非常用トイレの備蓄量が分かり、いざという時のトイレの不安から解放されます。一人暮らしから高齢のご家族がいる家庭まで、それぞれの状況に合わせた具体的な備蓄量と、失敗しない選び方を徹底解説します。この記事が、あなたの防災対策の一歩となり、いざという時も衛生的で快適な避難生活を送るための助けになれば幸いです。
災害時にトイレが使えなくなる理由
地震や台風などの災害が発生すると、水道や下水道のライフラインが停止し、自宅のトイレが使えなくなる可能性があります。特に、水道が停止すると水を流すことができなくなり、トイレが使えなくなるだけでなく、不衛生な状態が続き、感染症のリスクも高まります。
また、大規模な災害では、避難所のトイレも数が限られており、長蛇の列になることも珍しくありません。だからこそ、非常用トイレの備蓄は、食料や水と同じくらい、いや、それ以上に重要だと言えます。
失敗しない防災トイレの備蓄量と選び方
では、具体的にどれくらいの量を、どんな種類の防災トイレで備蓄すればいいのでしょうか?
1. 備蓄量の目安は「1人1日5回」
非常用トイレの備蓄量は、一般的に「1人1日5回分」が目安とされています。これは、トイレを大と小合わせて平均5回程度利用するという考え方に基づいています。
| 家族構成 | 3日間の備蓄量 | 7日間の備蓄量 |
| 一人暮らし | 1人 × 5回 × 3日 = 15回分 | 1人 × 5回 × 7日 = 35回分 |
| 2人家族 | 2人 × 5回 × 3日 = 30回分 | 2人 × 5回 × 7日 = 70回分 |
| 3人家族 | 3人 × 5回 × 3日 = 45回分 | 3人 × 5回 × 7日 = 105回分 |
公的機関が推奨する備蓄期間は最低3日ですが、ライフラインの復旧が長引く可能性も考慮し、できれば1週間分の備蓄があると安心です。
2. 非常用トイレの選び方
非常用トイレには、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルや家族構成に合ったものを選びましょう。
- 凝固剤タイプ: 既存のトイレに袋を被せ、用を足した後に凝固剤を入れて固めるタイプです。
- メリット: 普段使っているトイレをそのまま利用できるため、心理的な抵抗が少ないです。
- デメリット: 凝固剤や袋を常にストックしておく必要があります。
- 携帯タイプ: 袋や凝固剤がセットになっており、持ち運びが簡単なタイプです。
- メリット: 非常持ち出し袋に入れておくのに便利で、車中や外出先でも使えます。
- デメリット: 備蓄量としては少ないため、他のタイプと併用するのがおすすめです。
- 簡易トイレ(段ボールタイプなど): 組み立てて使うタイプで、便座や便器の役割を果たします。
- メリット: 既存のトイレが使えない場合でも、どこでも設置して利用できます。
- デメリット: 組み立てに手間がかかる場合があります。
防災トイレの保管とローリングストック
非常用トイレは、湿気を避け、冷暗所に保管することが大切です。また、防災食料品と同様に、非常用トイレも定期的に消費・補充するローリングストック法を推奨します。
ローリングストック法とは、例えば普段から使っているウェットティッシュやトイレットペーパーを多めに買い置きしておき、消費したら新しいものを買い足す方法です。これにより、災害時に備えながらも、無駄なく備蓄を継続できます。
まとめ
防災トイレの備蓄は、食料や水と同じくらい、あなたの命と安全を守る上で不可欠な準備です。今日から始める小さな一歩が、いざという時の大きな安心につながります。
この記事でご紹介した備蓄量を参考に、まずはあなたの家族に合った非常用トイレを揃えてみませんか?
今日からさっそく、防災トイレの備えを始めてみましょう。
防災リュックについて詳しく知りたい方はこちら
防災水について詳しく知りたい方はこちら
防災食料品について詳しく知りたい方はこちら
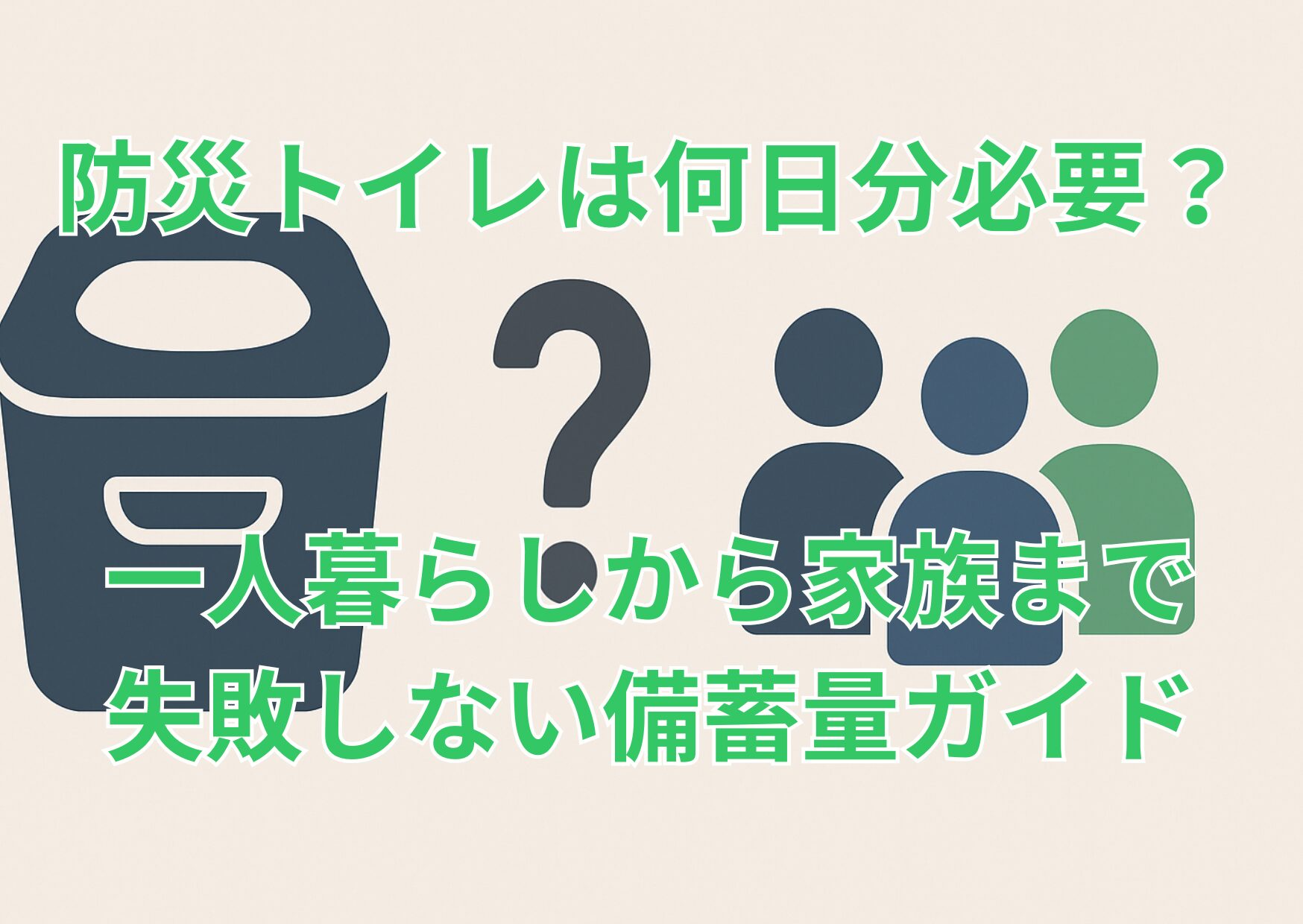

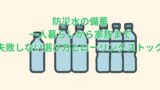



コメント