
もしも、大きな地震が起きて、仕事場と幼稚園で子どもと離れ離れになってしまったら…

電話が通じなくなったら、どうやって家族の安否を確認すればいいの?

あなたは、そんな切実な不安を抱えていませんか?
私自身、この不安は痛いほどよくわかります。私の父が土砂崩れに巻き込まれかけた経験から、防災の重要性は痛感していますが、備蓄品リストを完璧にすることよりも、「子どもの命を守り、家族が再会できるためのルール」を決めておくことの方が重要だと気づきました。
ご安心ください。この記事は、子育て世代のあなたが抱える最大の不安を解消するために作られた完全ガイドです。この記事を最後まで読めば、専門家の知恵と災害経験者の声に基づいた、「防災家族会議」で使える10の具体的なルールが手に入ります。大切な家族を災害の混乱から守り、いざという時も冷静に行動できるための、安心という恩恵を一緒に手に入れましょう。
なぜ子育て世代が「ルール決め」をすべきか?
子育て世代にとって、家族間のルール決めは、食料や水の備蓄と同じくらい、いや、それ以上に重要です。その理由は、子どもの特性と災害時の状況にあります。
1. 子どもは「ルール」で不安を乗り越える
子どもはパニックになりやすい反面、事前に決められたルールには忠実に従うことができます。「地震が来たら、まずこの場所に行く」という具体的なルールがあれば、親と離れていても動揺が少なく、安全な行動を取りやすくなります。
2. 親が冷静になるための「ガイドライン」
災害発生時、親自身もパニックに陥りそうになります。しかし、ルールがあれば、「今はまず安否確認の連絡ルールに従おう」「次は集合場所に向かおう」と、次に取るべき行動が明確になり、冷静さを取り戻すことができます。
3. 「命を守る」ための最優先事項
阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓から、家族間の連絡や避難所のルールが曖昧だったために、安否確認に時間がかかり、心身ともに疲弊したケースが多く報告されています。事前の話し合いは、家族の命と安全を最速で確保するための最優先事項なのです。
【核となる10のルール】家族で決めておくべきことチェックリスト
ここからは子育て世代の生活を想定し、学校・幼稚園・外出先といった、家族が離れ離れになりやすいシチュエーションをカバーする10のルールを提案します。
ルール1:連絡の最優先ツールを決める(171、SNS、アプリ)
災害時は電話がつながりません。安否確認の「最優先ツール」と「連絡係」を決めておきましょう。
- 第一優先:災害用伝言ダイヤル(171)
- 第二優先:災害用伝言板(web171やキャリアサービス)
- 第三優先:SNS(LINEやTwitterなどのメッセージ)
- 連絡係: 誰が誰に連絡するか、誰がSNSに情報をアップするか、役割分担しておきましょう。
ルール2:第一・第二集合場所を設定する
自宅の被害状況に応じて、どこで合流するかを決めておきます。
- 第一集合場所(徒歩圏内): 自宅が安全な場合の一時的な合流場所。(例:近所の公園の大きな時計台の前、馴染みのコンビニなど)
- 第二集合場所(広域): 自宅が倒壊・危険な場合の集合場所。(例:地域の広域避難場所、遠方の親戚宅など)
ルール3:子どもの迎えと引き渡しルールを明確にする
親がすぐに迎えに行けない場合を想定し、ルールを決めておきます。
- 迎えの担当: 誰が優先的に迎えに行くか(例:近所にいる親、祖父母など)。
- 引き渡しルール: 学校や幼稚園は、保護者以外の引き渡しを制限しています。事前に緊急連絡カードに登録されている人以外は迎えに行けないルールを伝えておきましょう。
ルール4:外出先での「おまもり」ルール
親子が買い物中や公園で離れてしまった場合の行動を決めます。大まかな行動指針を共有しておきましょう。
- 子ども側のルール: 「動かない」「近くにいるお店の人や制服を着た人に助けを求める」など。
- 親側のルール: 「その場から動かず、子どもが戻ってくるのを待つ」など。
ルール5:自宅で被災した場合の「3つの行動」
地震発生時の初期行動を、子どもにも分かりやすい言葉でルール化します。
- 「ダンゴムシのポーズ」で頭を守る。
- 「火は触らない」(火の始末は親が担当する)。
- 「すぐに玄関に集合」(家具が倒れていない安全な場所)。
ルール6:避難時の役割分担を決める
パニック防止のため、家族それぞれの役割を決めます。
- お父さん: 防災リュックの確認・持ち出し、車の燃料確認。
- お母さん: 貴重品(通帳、保険証など)と常備薬の持ち出し、子供の保護。
- 子ども(5歳): 非常用の笛を吹く、ペットのリードを持つ(ペットがいる場合)。
ルール7:防災グッズの場所を共有する
防災リュックや水、食料の備蓄場所を、子どもにも「ここにあるよ」と具体的に教えておきます。親が負傷した場合、子どもが自力で持ち出せるかもしれません。
ルール8:非常時のトイレ・食事のルール
避難先でのトイレと食事について、事前に伝えておきます。
- 「水が流せない時は、備蓄してある簡易トイレを使うよ」
- 「非常食は、普段のお菓子と違って大切に食べるものだよ」
ルール9:連絡が取れない場合の「お金のルール」
親が連絡不能で動けない場合、子どもや配偶者が動くためのルールです。
- 家族それぞれが少額の現金(公衆電話用の10円玉も含む)と保険証のコピーを持つ。
- 避難所でのルール(お金は使えない場合もあること)を伝えておく。
ルール10:年に一度の「防災家族会議」と訓練
ルールは決めたら終わりではありません。子どもの成長に合わせて、年に一度はルールを見直す日を設けましょう。誕生日や防災の日などをきっかけに、家族で訓練を実施し、ルールの定着を図ります。
子どもの不安を和らげる「話し合いのコツ」
防災は「恐怖」を与えるものではなく、「安心」を与えるものです。子育て世代が抱える「家族を巻き込む難しさ」を解消するコツをお伝えします。
1. 「ゲーム感覚」で楽しくルールを定着させる
- 宝探し形式: 「パパのスマホが切れた!連絡ツール(171)を探せ!」といったミッション形式で、ルールやツールの使い方を学びます。
- 役割訓練: 「お父さんは何係?」「お母さんは何係?」と役割を演じてもらうことで、当事者意識を持たせます。
2. 「防災リュック作り」を一緒に楽しむ
子ども自身に「リュック係」になってもらい、リュックの中に自分だけのおもちゃや好きなお菓子を一つ選んで入れさせましょう。リュックへの愛着が生まれ、いざという時もリュックを大切に持ち出そうとします。
3. 「絵本」や「動画」を教材にする
災害をテーマにした絵本やアニメを見て、災害が起きる理由や、その後の生活について語り合いましょう。恐怖心を煽るのではなく、「こうすれば大丈夫だよ」という安心感をセットで伝えることが重要です。
4. 褒めることで「前向きな習慣」にする
「今日の避難訓練、10秒でヘルメットかぶれたね!すごい!」と具体的に褒めることで、防災がポジティブな行動として定着しやすくなります。
災害時も慌てない!安否確認ツールの使い方
ルール1で決めた安否確認ツールの使い方を具体的にマスターしましょう。
1. 災害用伝言ダイヤル(171)
- 使い方: 局番なしの「171」に電話し、ガイダンスに従ってメッセージを録音・再生します。
- コツ: 自宅の電話番号など、共通の電話番号をキーに利用するため、家族全員がこの番号を把握しておくことが重要です。
2. 災害用伝言板(web171/キャリア提供)
- 使い方: 携帯電話会社やNTTのウェブサイトからアクセスし、文字で安否情報を登録・確認します。
- コツ: スマートフォンから簡単にアクセスできるため、モバイルバッテリーとセットで覚えておきましょう。
3. SNS・LINEの活用
- メリット: データ通信を使うため、音声通話が規制されていても繋がりやすい傾向があります。
- コツ: 家族間で「〇〇(SNS名)で『無事』と一言送る」といったシンプルなルールを決めておきましょう。
まとめ
防災は、「備蓄」よりも「ルール」が大切です。この記事でご紹介した10のルールは、子育て世代のあなたが抱える最大の不安を解消するための確実な一歩となります。
今日から始める小さな一歩が、いざという時の大きな安心につながります。さあ、この記事のリストを参考に、「防災家族会議」を開いて、あなたとご家族の安全を守るためのルールを一緒に決めてみませんか?
防災の基本について詳しく知りたい方はこちら
防災リュックについて詳しく知りたい方はこちら
防災トイレについて詳しく知りたい方はこちら
防災水について詳しく知りたい方はこちら
防災食料品について詳しく知りたい方はこちら
バッテリーについて詳しく知りたい方はこちら
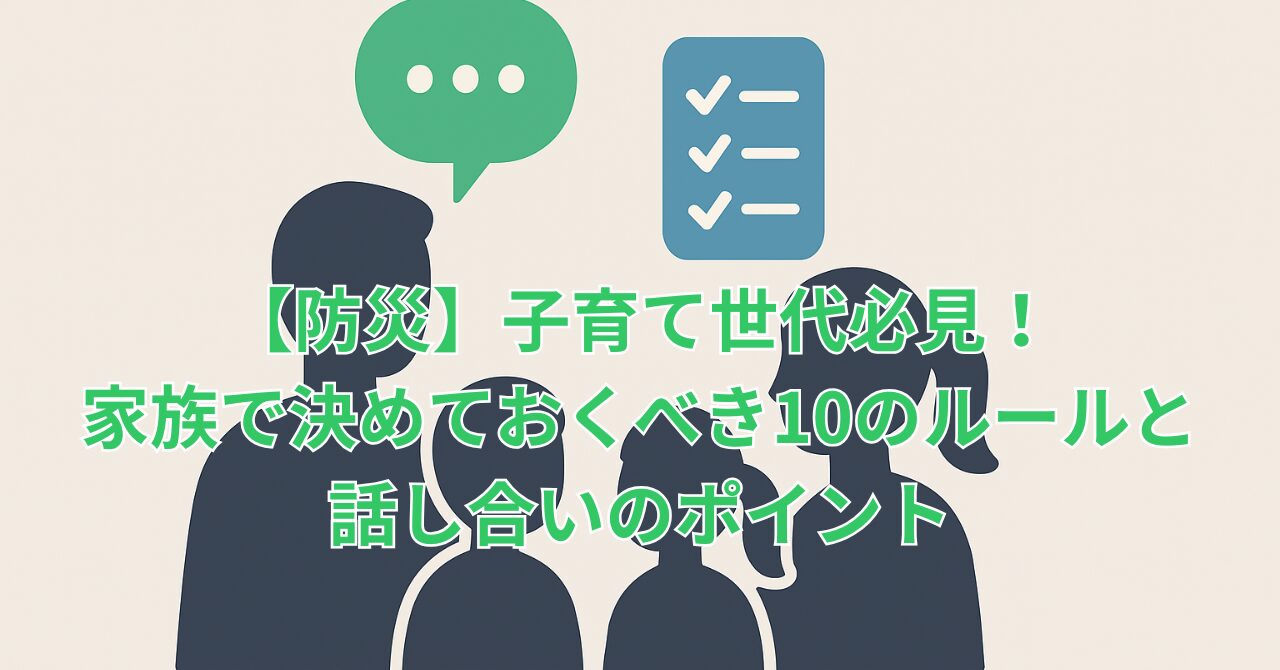


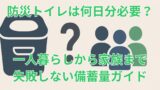
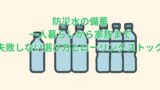




コメント